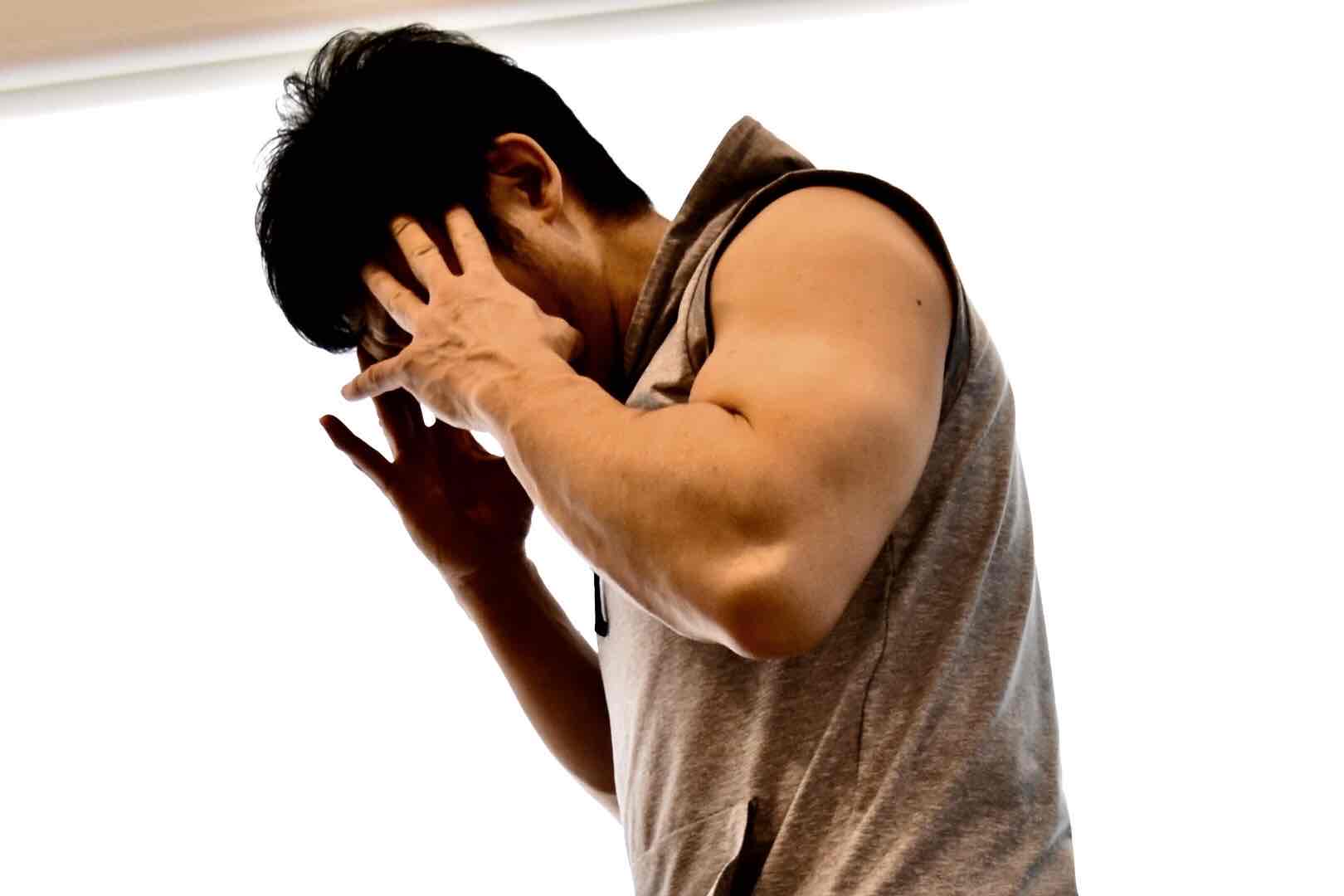
2025年10月10日
こんにちは、パーソナルジムSORAの森です。今回は、「飽きると脳疲労の関係」についてのお話しです。
普段、仕事、勉強、趣味などで「飽きる」という現象が起こることがあると思います。そこで「飽きる」と「脳疲労」について少し考えていきましょう。「飽きる」と「脳疲労」は密接に関係しています。簡単に言うと「飽きる」とは、脳が疲れているサインのひとつで、脳疲労が蓄積すると「飽き」が生まれやすくなります。
脳は、機能的に非常に細かい役割分担をしています。例えば、一つの物事をしている場合、同じ神経細胞が興奮してその細胞が酸化していきます。これを防ぐためのアラームが「飽きる」という感覚です。
例えば、車の運転をしている場合、車を運転するのが好きな人でも、1時間2時間運転し続けると飽きてしまう人も多いでしょう。特に直線が連続して信号のない高速道路での運転は、単調な作業ですから、脳の同じ神経回路を使っていると考えられています。
運転のような作業でも仕事でも「飽きた」という感覚を無視すると、やがて頭がボーッとしたり、全身がだるくなったりといった症状が表れてきます。運転中の交通事故のリスクも高くなります。そうなる前に「飽きた」と感じたら、休息をとったり別の課題に取り組むなどして脳の疲労を和らげることが大切です。
飽きるとは、同じ作業を繰り返す事で、脳がその刺激に対して反応しなくなる状態です。脳にとって「意味がない」「新鮮味がない」と感じると、やる気や集中力が下がり、興味を失います。
脳疲労は、脳の情報処理機能が過剰に働き、回復が追い付かなくなる状態です。特に前頭葉(思考や判断、感情の制御などを司る)が疲労することで、以下のような症状が現れます。
・集中力の低下
・やる気の喪失
・情緒不安定
・記憶力の低下
【飽きると脳疲労の関係】
脳疲労が進むと・・・
・同じ作業を繰り返す⇒前頭葉が酷使される⇒脳が「新しい価値がない」と判断し興味を失う
・報酬系(ドーパミン分泌)が鈍化⇒やっても快感が得られず「飽きる」感覚が増える
【脳が飽きを感じやすい例】
・同じ仕事、作業を長時間連続でおこなう
・SNSの過剰使用(情報過多)
【飽き、脳疲労を防ぐには】
・休憩をこまめにとる
・自然に触れる、散歩する
・寝る
・新しい刺激を入れる(新しい趣味や音楽など)
・「楽しい」と感じる作業とのバランスをとる
【まとめ】
・飽きるのは、脳が疲れているサイン
・脳疲労が蓄積すると、同じ作業が苦痛になり「飽きた」と感じる。
・脳疲労を防ぐ為には、休息、変化、楽しみのバランスが重要
以上のことを意識して、仕事、勉強、趣味などを継続していきたいですね。
大阪市中央区松屋町、谷町4丁目、堺筋本町エリアにある「パーソナルジムSORA」では、「理論と実践を兼ね備えたボディビル優勝経験のある院長によるトレーニング指導。」「解剖学、生理学、運動学、など体のメカニズムを熟知した国家資格によるトレーニング指導。」「トレーニングと治療の融合」などを特徴としております。経験豊富なパーソナルトレーナーをお探しの方は、是非、お声掛けください。
只今、無料カウンセリング受付中(要予約、カウンセリング時間約30分)
森 健浩
パーソナルジムSORA パーソナルトレーナー
そら鍼灸整骨院 院長
柔道整復師 鍼灸師
1995年大阪ボディビル選手権バンタム級 優勝



